

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
♪さらば夏の日 1971.10
DU SOLEIL PLEIN LES YEUX
作詞:早川清至 作曲:Francis Lai 編曲:宮川 泰
演奏:宮川泰とルーパス・グランドオーケストラ
録音:1971.06.09 キングレコード音羽スタジオ
| 一般知名度 | 私的愛好度 | 音楽的評価 | 音響的美感 |
| ★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
今回の随想は、その名の通り、いきなり大脱線することに致します。
ちゃんと後で、収束しますので、しばらくおつき合い下さい。
最近、この本を買いました。宇野功芳というお名前が懐かしかったからです。
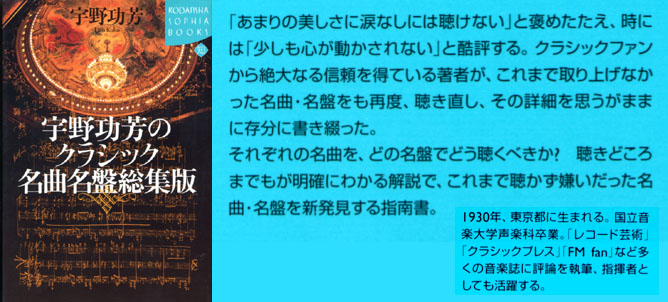
まだ、この方はお元気でご活躍中なんだなあ、と嬉しくなってしまいました。
どのレコードだったか忘れましたが、ライナーを書かれていて、それが面白く、
以後、CD以前の時代に単行本を買い求めていくつか読んだことがありました。
とにかく熱気のある読み物としてもドキドキするような過激な文章が満載です。
勿論、クラシック音楽をメインにしているわけで、ふつうは縁遠い存在でした。
両親のどちらもクラシック音楽なんか聴くような高尚な家に生まれついていませんし、
学校の音楽鑑賞なんてのもかえって嫌いになるための授業のようなものでした。
何故、クラシックにも関心を持つようになったかといいますと、原因はオーディオ。
ザ・ピーナッツのレコードを自分が一番好きな状態で聴ける装置を追求したところ、
タンノイという英国の世界最古のオーディオ・メーカーの製品に遭遇しまったのです。
別に鳴りっぷりがボーカル向きで生々しかったということではないのです。
その音色の気品に惚れてしまったのです。
ソフトな聴きやすい音とは対極にある、厳しく威厳のある響きでした。
これで歌謡曲を聴くという人はあまり居ないだろうとも思いました。
しかし、以外と、これで美空ひばりなど愛好する人が居たと知ったのはずっと後で、
確かにコロンビア・レコードは検聴(モニター)スピーカーにこれを使ってました。
別にプロが使うから、良い音だというわけではありません。
良い音とは聴く人が好きな音なので、モニターというのは「不具合が無いか聴き取る」
ことが目的なのであって、楽しむものではありません。
そうなのですが、一部の日本人はこのモニタースピーカーが大好きなのです。
同じようにアメリカにはJBLというモニタースピーカーの老舗があります。
でも、イギリス人の殆どはタンノイを知らないし、アメリカ人はJBLを知りません。
メーカーも日本には随分沢山のスタジオがあるものなんだなと驚いて出荷したのです。
まさか、自宅の畳の六畳間などで聴いているなんて夢にも思わなかったのです。
だから、この超ハイクオリティの音響メーカーは日本人が育てて教育したようなもの。
両社の技術者は日本のユーザーと心が通っていたのです。
我が国のスピーカー・メーカーは現在、ビクターが残っているくらいで殆ど撤退。
結局、音楽を鳴らして訴える何かの要素が欠落しちゃっていたからです。
タンノイもJBLも非常に強力な磁石を背負っていて、これは過剰なほどの強力さで
バランス的には神経質で、なかなか滑らかには鳴りません。
三ヶ月くらい鳴らしてないとほぐれてこないので、最初は酷い耳障りな音がします。
ところが一旦、具合良く鳴り出すと日本のメーカーでは絶対得られない妙音となって
音楽的に鳴るというのはこういうものか、と感動することになります。
工業製品としての製造品質は断然日本製が良いし、見栄えもするし、歌謡曲などを
聴いている分には何にも不満はなく、値段も手ごろなのです。
でも、肝心の音に魅力がないのです。その魅力の違いに気付くことは不幸なのかも?
知ってしまったら、後戻りは出来ないのです。
生々しいというのとはちょっと違います。ある面で「生」より魅力的だからなんです。
冷静に聴けば、随分と偏った変な音かも知れず、多数決風に皆で決めて作ったなら
こういう個性的な音色にはなりっこない、と思われます。
強力なリーダーが居て、その人の決めた音色がずっと徹底しているのです。
タンノイのスピーカーのオリジナル設計は1947年で私の生まれた年なのですが、
最新作のシステムに至っても音色は不変で、性能が良くなっているだけです。
こんなことは日本のどのメーカーにも全くありません。型番が違ったら音色も違う。
たまに素晴らしいものが出来ても、その良さが次のモデルでは消えてしまうのです。
楽器と同じように作らねばならないという意識がないからだと思います。
電気製品としての品質は日本製は抜群です。でも良い音の出る楽器ではないのです。
ザ・ピーナッツの歌声そのものの迫真性は国産のスピーカーで何も問題ありません。
むしろ、国産の音の方が「正しく」鳴っているのかも知れないのです。
しかし、タンノイが奏でるザ・ピーナッツの歌は神格的で麻薬的で鳥肌が立つのです。
そもそもレコード音楽を愛好することに伝統がある国イギリスの女王陛下の楽器です。
国営放送局の常設スピーカーが歌謡曲など鳴らした結果等メーカーは知るわけがない。
ザ・ピーナッツのレコードを聴くには最も不適切なスピーカーかも知れないのですが、
日本製のように当たり前には鳴らないところが凄い魅力でした。
ピーナッツの歌う口元が実際の彼女達の唇の大きさで聴けるし、位置もぴったりと
決まって、そこで歌ってくれるのです。そもそもオペラの再生に定評があるのです。
「恋のバカンス」での金管楽器は実際に鳴っているスピーカーも金属のホーンだから
その音色が素晴らしく華麗で歯切れが良く、聞き惚れてしまいます。
そして「こっちを向いて」での弦楽器の哀切さがたまりません。涙が出ました。
特に弦楽器の音色に関してはバイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバスのすべてが
素晴らしい音色で鳴るのです。それは本物より綺麗な音かも知れないほどなのです。
このスピーカーがクラシック音楽も鳴らしてみたいという動機となったのです。
そういうことですから、クラシックが好きで聴き始めたのではなくて、スピーカーが
そのジャンルを呼び込んだとしか思えません。音楽教育者みたいなスピーカーです。
モノラル時代に誕生したスピーカーなので、電蓄的な趣もあって、モノラル盤でも、
割と楽しめる面があって、伝説的名指揮者フルトヴェングラーのレコードライナーで
前述の宇野功芳さんの名解説を読む巡り合わせになったのだと思います。
自分が知らない曲でもこの方の文章に接すると、文章だけでその曲を味わえる気分に
なった気がして、その曲を是非聴いてみたい、という気にさせてくれるのです。
この本を讀んで吃驚したのは、宇野功芳さんのお父様が漫談家の牧野周一だったこと。
有名なことだったのかも知れないのですが、それが売り物じゃないので迂闊にも私は
この事実を知りませんでした。だって苗字が違うんだもの仕方ないですよね。
宇野功芳さんとザ・ピーナッツと何の関係があるんだ!
そろそろ焦れた頃だと思うので、こちらを見て下さい。
↓
http://peanutsfan.net/makino.html
当時のキングレコード部長さんだった、牧野剛さんのお父様も牧野周一さんなのです。
すなわち、宇野功芳さんと牧野剛さんはご兄弟であった、ということです。
これには驚きました。
漫談家の牧野周一さんの芸風は私も大好きでした。
無声映画時代の映画の弁士をおやりになっていた時期もあったとか。
当時は活動大写真と言ったので、その弁士は「活弁(カツベン)」と称し楽士と共に
映画の解説から何から全部やっちゃうエンターテインメントであったらしく、弁士が
映画館の入りを左右するという重要な役割であったそうです。
ある時、母から祖父は逗子の映画館で、この活動弁士をやっていたと聞きました。
それを聞いたのは、私が大勢の人の前で発表や説明などをすることが苦にならないと
いう面があり、得意であって、そんな自分が信じられないと母に語ったからでした。
「それはね、血が喋らせているんだね。隔世遺伝というものだね」と言うじゃない。
人付き合いは苦手で、引きこもり系だし、オーディオ、パソコン、アニメが好きな
今流行りの「アキバ系オタク」の先駆者みたいな自分で、引っ込み思案な人間です。
なのに....数人が相手ではちゃんと話せないのに、相手が発言出来ない状況下では
多くの聴衆がいればいるほどファイトが湧き、熱弁がふるえるのです。
壇上に立つ前までは足が震えたりするのに、adrenalineが急に分泌するのだろうか、
奇跡的な活力、能力、勇気に満ちあふれてきます。
上気してはいるのですが、頭脳は素晴らしく明晰となって、クロック周波数の高い
パソコンのように、今、口から出ている言葉よりも数行先まで意識下に明確になり、
聴衆の反応まですっかり見渡せています。受けているか、ということも意識します。
寝ていた人も起きてしまうのがわかるのです。
お前、商売間違えたのと違うか? なんて後で言われますが、それは違うのです。
原稿というか台本というか、そういう事前の準備は物凄く大量にやって置くのです。
それに自分の仕事のことを説明するのですから、自分より良くわかっている人間は
他にいない、俺がプロだと自負しているから中身については恐くはないのです。
だけど、話芸が得意じゃないのだから、そういう仕事は出来ません。
とにかく、そういう見えない糸で、あちこち縁があるんだな、と感じた次第です。
さて、やっとメインテーマの楽曲の紹介に入りますが、フランシス・レイの名曲で
あって、曲については、何もコメントしなくて良いでしょう。
作詞の早川清至さんというお名前はピーナッツの歌ではあまり馴染みではありません。
早川清至というのはペンネームで、シャンソンのレコードの解説や対訳をされていた
方なのだそうです。エールフランス国営航空会社に勤務されていた佐川清治が本名。
編曲もLP丸ごと宮川先生ですし、オーケストラも先生の意図にそって集められたと
思われる名人集団なのでしょう。技術的にもあらゆる面で文句のつけようがない出来。
このような素晴らしい内容のLPなのですが、宣伝もしないし、テレビなどの番組で
紹介するわけでもなく、投資の回収など眼中にないような感じには驚きます。
殆どスタッフの自己満足のために、いいものを作って残そうとしているかのようです。
恐らく沢山の売上があったとも思えずCD時代になって不要なレコードが売られても
中古市場にもそんなに出回らないのではないかと推察します。
渡辺社長から「牧野君に預けよう」と返事を頂き、天にも昇る心地がした牧野さんは
恐らく、この初心をずっと忘れずに、ザ・ピーナッツのレコード作りには最大限の
努力を惜しまなかったのではないかと私は思います。
そういう愛情がこのLPには溢れています。それは引退するまで、いや、引退後も
続いているのではないか、とさえ私は感じます。
ザ・ピーナッツとの契約を取り損ねた犬のマークのレコード会社のプロデューサーが
現役を退く前に、ザ・ピーナッツの録音をするのが夢だったと(恐らく牧野さんに)
打ち明けて、本当に特別に例外中の例外で、「大阪の人」の録音をV社のスタジオで
行ったというのも、同業者だけに、その心情を理解出来合った仲間であったからだと
思うのです。そんな風にピーナッツのレコード作りには、恐らく現在のそれとは全く
違った心のこもった良い仕事をしていた時代だったろうと思います。
ザ・ピーナッツの録音を疎かにするような人間はキングレコードの社員ではない、と
言ったら大袈裟かも知れませんが、会社としても記念碑のような宝物とも思えますし、
ピーナッツの魅力の集大成の感もある、このLPにはザ・ピーナッツさんご自身でも
素晴らしいレコードを作ったんだな私達は..と何十年後でも誇りに感じているのでは
ないかと推察します。また、多くのスタッフを思い出し感謝していることと思います。
(2004.11.3記)