MORE THEN ANYTHING
原曲:Tchaikovsky(Swan Lake Ballet) ポップス版原曲:Bobby worth
作詩:千家 春(=岩谷時子) 編曲:宮川 泰
演奏:東京キューバン・ボーイズ
録音:1960.05.26


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
♪白鳥の恋 1960.8
MORE THEN ANYTHING
原曲:Tchaikovsky(Swan Lake Ballet) ポップス版原曲:Bobby worth
作詩:千家 春(=岩谷時子) 編曲:宮川 泰
演奏:東京キューバン・ボーイズ
録音:1960.05.26


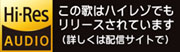
| 一般知名度 | 私的愛好度 | 音楽的評価 | 音響的美感 |
| ★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
この歌は大好きです。絶品だと思います。
別のスレッドで私の捨て難い曲をずらっと並べましたが、トップに挙げています。
これを聴くとあまりの感動で体温が上昇するようなそんな感覚に襲われるのです。
ザ・ピーナッツ初のステレオ録音です。演奏との一糸乱れぬ同時録音でもあります。
また、この時代に、ステレオ録音された歌謡曲・ポップスの類いは無かったのでは?
もしかすると、このジャンルでは世界的にも最速の一枚になるのではないでしょうか。
で、ありながら、この録音が耳を疑うような見事な出来栄えなのです。
デジタルだろうと何十トラックだろうと、どんな最新機材を駆使しても、このような
音質にはならないでしょう。これは技師のノウハウとハートの問題だからです。
これを聞いたら、そこらのヘボ録音屋どもはコソコソ逃げ出すのではないかしらね。
歌がまた素晴らしい。
まだ若々しくフレッシュなピーナッツですが、こんな見事な歌唱が出来たのです。
歌とスキャットの瞬時切り替えも滑らかで、二重録音かと思う程ですが、違います。
なんとロマンチックで可憐で、しかも切ないほどに美しい声音なのでしょう。
しかし、残念なことに当時の私はまだ中学一年で、一人で日劇など行けなかったし、
テレビでこの歌を歌っているピーナッツの記憶がないのです。(泣)
それに学校の「音楽」の時間の器楽演奏が苦手以上に恐ろしかったのです。
ハーモニカが吹けなかったのです。今でも、あれを見るとぞっとします。
180度転換してバンドなんか始めたのはずっと後の勤め人になってからです。
そんなだから、音楽は大して好きじゃなかったのです。
それでも通信簿はたいがい5でした。それは歌が上手かったんです。
親父が家に酔っ払いの仲間を連れて来ると歌わされたのが「ここに幸あり」でした。
ボーイソプラノの見事な歌いっぷりだったようです。(今や面影もないが:笑)
そんなわけで、テレビ番組としてはピーナッツの出演を殆ど見ていた筈なのですが、
歌手のファンになるなんて人種ではないと思っていたので、無意識だったのです。
でも、妹の観察によると、ずっとピーナッツが好きだったみたいと、と言います。
あの「白鳥の恋」のジャケット衣装を身に付けて歌うピーナッツは見たかったです。
見てるかも知れなくても、記憶に無いのは見れども見えずという情けない話です。
レコードを聞きながら、このジャケットを眺めていると、そんな幻覚が見えるような
そういう幻想的な甘酸っぱく、じっとしていられない切なさがこみ上げてくるのです。
演奏の東京キューバン・ボーイズがまた奇跡的な名演を聴かせてくれます。
元々がこのバンドはクラシックの曲をラテンタッチに楽しく聴かせるテクニックを
持っているし、そういうレコードも出している、いわばお得意の分野なのです。
だから、この演奏は素晴らしい出来です。鬼気迫るというような村正の切れ味です。
録音の良さに支えられていると思いますが、トランペットもストレート・ミュートと
カップ・ミュートそれにオープンを巧みに使い分けていて表情も多彩です。
トロンボーンの和声も美しいし、ここぞという所のバストロンボーンが利いています。
フルート、クラリネット、サックスと持ち代える木管群も綺麗な響きを醸し出すし、
これが伴奏なんだろうか、という最高のレベルです。
曲そのものはチャイコフスキーの「白鳥の湖」なのですから、良くて当り前です。
「くるみ割り人形」「眠れる森の美女」のバレエ音楽も誰にでも聴きやすく馴染める
音楽ですので、上質なムード音楽として愛好されるのも良いのではないかと思います。
こんな少女趣味濃厚な世界の美的感覚を脳内に持っていてはその驚異の感性に人格が
壊れてしまわなかったのだろうかと思われるほど、人間業ではない甘美さの極みが
聴けます。こういうのにも私はめっきり弱くてメロメロになってしまいます。
ところで、何故、月影のナポリとのカップリングEPなのに、ジャケット写真の方は
B面の白鳥の衣装なのでしょう。やはりこれはなかなかの思い入れが感じられます。
私も、B(ランク)面というイメージはないのです。両方が凄いのですからね。
あ、そうだ、アレンジの宮川センセをすっかり忘れておりました。
どこがどうとか言うレベルじゃなくて、もう全然この流れしかないでしょうという
ばっちり決まったアレンジです。こういうロマンティックなのは大得意なのでしょう。
とにかく奇跡の一枚としか言いようのないスタンディング・オベーションものです。
投稿日:2003/08/10
今日は、気まぐれで色々と「白鳥の湖」のCDを聞き比べてみたくなった。
真っ先に聴いたのが、カラヤン指揮ベルリンフィルという一つの定番のようなやつ。
これのなかでも超お馴染みの「情景/第2幕」は、このザ・ピーナッツの歌の原形。
このCD(1971年1月録音)でのオーボエ・ソロの音色が圧巻なのだ。
楽器が鳴るんじゃなく啼いている。絶世の美女が泣いているかのようでおろおろする。
頼むから、そんな音で吹かないでくれ。もう、たまんなくなってしまうじゃないか。
大真面目で、この世の響きとは思えないのだ。こんな音色は他では絶対聴けない。
リードの削り方とか何かが違うのだろう。高音に進むにつれて、か細く震えてしまい、
まるで演歌の節回しのようにハートをきゅっと締め付ける。こんなのありかよ〜!
なんか、空間が歪んでしまうかのような愁嘆場の空気感をこの奏者は作ってしまうが、
それでいい、それがいい、とカラヤンさんはそのフィーリングを尊重するかのように
オーケストラのコントロールをイメージが繋がるようにやっている。
木に竹を接ぐというようにならないし、かつ、そこから雄大な音楽へと展開させる。
全体で大芝居をうっている。この人はジャズとかポップスも聴く人のようで映画の
音楽なんかに絶対に負けてたまるかと壮絶華麗な演奏を聞かせてしまう腕がある。
初めて聴いた人の耳にもこびりつかせるように、ほら、ここが、この音が聴き処と
音楽を鳴らしながら、音で解説をしているようだ。
うわっ、こんな大仕掛けにやるのか、という面もある。もちろん楽譜通りなんだが、
それでも音楽的パフォーマンスが絶大。まさに大スターの艶技。聞き惚れる。
同じカラヤンさんで、今度はウィーンフィル。(1965年録音)
もろウィーンフィルの音。日溜まりのような、風呂に浸かってるような心地よさ。
もうこれだけでいいじゃん、という感じなんだが、アクセント付けましょうねとか
スタッカートはもっとはっきりね、とか指示があって、まあ、努力しましょうかね
という感じで演奏が進むが、ちっともカラヤン指揮らしくはない。
ワルツになると決してウィーン風にやるわけじゃないが流麗でチャイコフスキーの
ワルツって素晴らしいなあ、と、うっとりさせてしまう。
ソロも飛び出さないし、金管もハーモニーに撤するので快感に流されやすい。
響きだけで満足しちゃう感じで演出臭さが後味に残らず、甘美さだけが残る。
今度は同じウィーンフィルでジェイムズ・レヴァイン指揮。(1992年11月録音)
演奏は上手いのだが、テンポが自分には不自然な感じがするところがある。
しかし、録音は素晴らしく良い。明晰だが耳にきついわけじゃない。
ウィーンフィルの音色の魅力の種明かしを聴いているような感じもする。
凄いのは終曲近くでの大太鼓のサウンド。ズドンと本当の重低音で地響きする感じ。
これデジタル録音のせいなのだろうか、お勝手にいた家内がびっくりして出て来た。
タンノイの38センチ/ウーハーと40キロ近い重量の300Wアンプの底力か?
録音に入っていたら出る。出す時は出す、という恐ろしい面を初めて体験した。
こういう音は、ザ・ピーナッツのレコードには入っていません。(笑)
さて次はレコード盤なんだけど、アンセルメ指揮スイスロマンド。(録音年不明)
ステレオ初期なのに音質は良い。ロンドンレコードは録音の良さに定評があった。
アンセルメ=バレエ音楽の神様と称され、当時は天下一品であり敵無しの大評判。
だけど、聞かせ処のオデットとジークフリートのパ・ド・ドゥの曲がいまいちだ。
チェロはまあいいんだけどバイオリンがどうも気に食わない。
もっと流麗に甘美に、そしてゆっくりでもリズミカルに演奏してもらいたい。
素人耳なので、素晴らしい演奏かもしれず、的外れかも。無責任かなあ。
次は、意外かもしれないが、お薦めに近い。オーマンディ指揮フィラデルフィアだ。
録音は1961年10月と古いが、なんせ、初めて電気録音をし、初めて放送の演奏をし、
初めて映画に出た、そういうオーケストラですから録音の何たるかを熟知した集団。
その結果に破綻などなく、素晴らしい安定感と安心感を聴く人に与えます。
実際、腕前は世界最高峰という評価(ラフマニノフ)もあり、緊張感がないのは
技術レベルが極めて高いからでしょう。
演奏はチャーミングで気取りがなく、テンポ一つとっても自分だったらこうしたい、
そんな感覚とフィットする馴染みやすさがあります。
シルキー・トーンとよばれた芳醇で滑らかな弦楽器と、それに馴染んだ木管楽器、
金管楽器もとても柔らかくて、どきっと驚くようなことがなく、まるで天国にいる
ような夢幻の響きが聴けます。
この指揮者は40年ほど、どこにも行かずに常任でした。お人柄も良いのでしょう。
音楽もそういう感じです。受け狙いは他の指揮者や楽団に任せたという達観ぶり。
こういう愛らしい曲を演奏したら、ピカ一なのかな、と私は感じました。
全曲盤がないのが残念。そもそもオーマンディさん、忘れられてます。無念。
実際、ほんとうに癒し系だ。今の世には必要な音楽なんだと思うけどね。
最後は自分の中の真打ち登場です。
http://www.hmv.co.jp/product/detail/2524454
ゲルギエフ指揮のマリインスキー劇場(昔の名前はキーロフ歌劇場)管弦楽団です。
名前からも分かるようにチャイコフスキーはロシアの作曲家です。
今まで聴いてきたのは、ドイツ、オーストリア、スイス、アメリカ、なんですから
全部外国人の演奏でした。クラシックはもうグローバルなものなので国籍なんてもん
関係ないといえば、その通りなんですが、じゃ本場もんはどうなんだろう。
いやはや、やっぱご本家は一味違うという感じはあります。
なんか自信たっぷりという感じ。風土というか、土臭いという雰囲気も出てます。
録音も良い。ものすごく自然で生々しい。ハイファイ調じゃなく瑞々しいのです。
CDなのにSACDのように音の中身が濃い感じで、音を拾っているというよりも
空気を運んで来る感じが素晴らしい。木管楽器など眼に見えるようなのだ。
演奏がまた細部に強烈にこだわっている。
第一幕のワルツでの、たった一音符をちょっと伸ばすだけの、そのことの重大さ。
これは見事にやられたね。これだけでノックアウト。
【スターダストをもう一度】の文中に、こういう箇所あったでしょ。覚えてるかな?
「次に移る動作をするじゃない。われわれがよく″アンド・ワン″って言うんだけど、
その流れがピーナッツはすごく奇麗なの」(土居甫)
これこれ、これと良く似てる感じのこと。これを音でやってる。
これで、ああ、バレエ音楽なんだよ、これ、絶対これ、いい。こういうことやってる。
実際にオーケストラ・ボックスでマリインスキー・バレエ団の伴奏をやっている強み。
それと、プロの音がする。
プロなんだから当り前なんだけど、なんちゅうかこの、強靱な楽器の音色がするんだ。
毎日、ガンガン鳴らしている。やわな美音じゃない。もっと芯がある図太い音がする。
このような中低音がゴリゴリ響く、この表現はなんなのだろう。
マリインスキー劇場管弦楽団の音なのだろうか、録音技術の進化なのだろうか。
とにかく、この鳴りっぷりは見事なもので生演奏を聴くような臨場感を感じさせる。
バイオリンなどは普通レコードでもCDでも細めの線のようにたなびいて鳴るのに、
ここでは基音と同時に倍音以外に低い力感のような音圧を押し出して来る。
このような存在感が高域にさえあるものだから、ビオラ、チェロ、コントラバス等の
共鳴部の体積の大きな楽器では凄まじいことになる。
低音楽器がパワフルに弾力的に鳴ることの快感がこんなに魅力的とは思わなかった。
お酒は飲めない私だが、例えれば今まで聴いて来たオーケストラの音色は清酒であり、
ここで聴けるサウンドは地酒の濁り酒みたいなもの。野性的でスリリングなのである。
澄んだ美しい音色ではない。逞しい生命感が迸ってくる。
それに何やら付帯音がやたらに入っている。鼻息とか譜面を落とした音とか呟きとか。
こういうのは普通は録音の失敗じゃないかと思ってしまうが、そこにも活き活きした
人という生き物が関与している有様が聴けて、なんとなく頼もしかったりもするんだ。
そういうわけで、華麗で豊潤というのとは違うが生命力のある演奏だと思う。
上手いというよりも力強いタフさがあり、百戦錬磨の職人の実在感たっぷりの演奏が
聴けるのが痛快である。アカデミックなのではなく体育会系の音が圧倒してくるのだ。
今生まれた音楽というイメージがして、クラシック=古い懐旧的なとは方向が異なる。
500グラムのステーキでも食ってから演奏してんじゃないのかと思えるほど体力と
気力のエネルギッシュさが音化されてサウンドのオリンピックのようでもある。
とにかく粘っこい。次の音に入る寸前まで弓から力が抜けてない。そんな感じだ。
これは聴き応えがある。最初を聴くともう最後まで止められなくなる。病付きです。
(2008.7.7追記)
